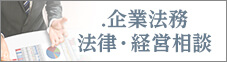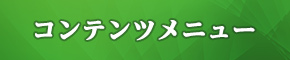遺留分について
Contents
遺留分とは一定の範囲内の相続人に最低限保障されている相続分のことです。
自分の財産は遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。
法定相続人の中の特定の人や、法定相続人以外の第三者に全財産を遺贈することも可能です。
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。
遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障されているのです。
では遺留分の権利は誰が持っているのでしょうか?
遺留分権者
遺留分の権利を持つ人を「遺留分権者」といいます。誰でも遺留分を有する訳ではありません。
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。
子と配偶者が相続人場合
| 子 | 4分の1 |
|---|---|
| 配偶者 | 4分の1 |
※ 法定相続分の2分の1
※ 配偶者が死亡している場合は子が2分の1
父母と配偶者が相続人の場合
| 配偶者 | 3分の1 |
|---|---|
| 父母 | 6分の1 |
※ 法定相続分の2分の1
※ 配偶者が死亡している場合は父母が3分の1
配偶者のみ
| 配偶者 | 2分の1 |
|---|
※ 法定相続分の2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人
| 配偶者 | 2分の1 |
|---|---|
| 兄弟姉妹 | なし |
遺留分を請求する
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、侵害された遺留分に相当する額の金銭を請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額を請求するには、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。
請求先は、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求をします。
また請求は、相続開始より10年で消滅します。間があいてからの遺留分侵害額請求は、後々のトラブルに発展することが多いので、できるだけ早く請求しましょう。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求をする場合は、必ず内容証明で請求されることをお勧めします。
内容証明できちんと証拠にしておかなければ、後に、遺留分侵害額請求をしたのかどうかで争うことになりかねません。
遺留分侵害額請求をして相手が請求に応じてくれれば良いのですが、殆どは簡単には応じてくれません。
このような場合には、家庭裁判所で調停、審判ということになります。

弁護士としての経験から言うと、遺留分侵害額請求をする場合は殆どが揉めますので、覚悟が必要と言えるかも知れません。
遺留分侵害額請求をする際は、弁護士に相談した上で行うのが良いと思います。
遺留分を請求されたら
相続人が遺留分を侵害されたとして、遺留分に相当する額の金銭を請求する権利を遺留分侵害額請求権と言います。
もしあなたが被相続人の財産を相続したとして、相続人から遺留分を請求されたらどうすれば良いのでしょう。
原則として、遺贈を受けた者は、あなた以外の相続人に法律上与えられた最低保証である遺留分を請求された場合、その分を渡さなければなりません。
たとえその相続人が、被相続人が存命時に全く関与していなかったとしても、遺留分は相続人に認められた正当な権利ですので、請求されたら拒めません。
遺留分侵害額請求がなければ、あなたがそのまま全部をもらって問題はありません。
あなたが相続人で、被相続人と相談して遺言を作成する場合、遺留分を侵害する内容の遺言は遺留分侵害額請求を受ける可能性があることをしっかりと覚えておきましょう。
できれば他の相続人の遺留分を侵害する遺言は避け、どうしても遺留分を侵害する内容の遺言をする場合は、遺留分を巡る紛争への対策を考えておく必要があります。
遺留分を請求された場合の対応は、専門家である弁護士に相談するのが良いと思います。
遺留分侵害額請求をされないために
相続人から遺留分侵害額の請求されないためには、どのようにすれば良いのでしょう。
その遺留分を請求されないためには、2つの方法が考えられます。
遺言書に最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をする
具体的には「私の遺産については、妻に1/2を、子どもに3/8を、前妻との子には1/8を相続させる」などのように遺言をすることです。
こうすることで遺留分侵害額請求はされないで済みます。
結果的に相続財産の一部を渡すことにはなりますが、こうした遺言を残すことが争いを生じさせない方法と言えるでしょう。
遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と遺言の中に書く
このように書くことで「それが被相続人本人の強い意志であれば、仕方ない」と思われる等、精神的に効果を与えることができるケースがあります。
しかし、この方法の欠点は、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても、それは何ら法的効力を有するものではないということです。
したがって、相続人はその遺言に拘束されず、遺留分侵害額請求ができるのです。
どちらの方法をとるにしても遺言書を作成する際は、遺留分のことを加味して作成する必要があります。
お困りのことがございましたら、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ
24時間受付